小学生の男の子・女の子の反抗期!成長の証へのNG対応は?
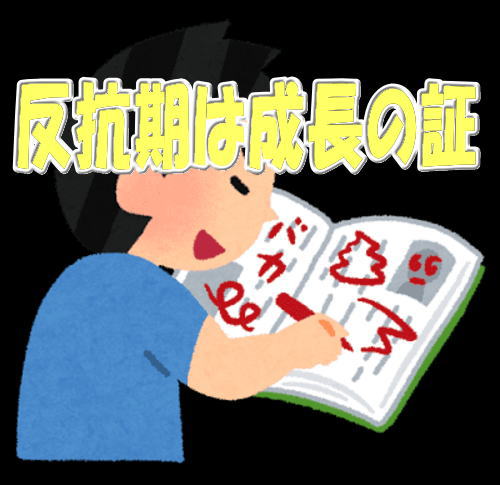
昔は素直でいい子だったのに・・・。
何でこんな風になっちゃったの・・・。
高学年の保護者の方から時々聞く言葉です。
家で親の言うことを全然聞こうとしない。
出てくる言葉は反抗する言葉ばかり。
私の育て方がいけなかったのか。
時にはそんなことを思ってしまうこともあります。
でも安心してください。
それはちゃんと子どもが成長している証です。
いわゆる反抗期というやつですから。
ただ、この時期の対応を間違えてしまうと、
いざ大きくなって子どもと向き合おうとした時に、
上手くいかなくなってしまいます。
今回は反抗期の子どもの姿と、
その対応について書いていきます。
反抗期って何で起きるの?

反抗期というのは、成長の過程だと言われています。
簡単に言うと、「親からの脱却」と言えるでしょう。
子どもは親や先生たちといった大人から、
あれはああしなさい。これはこうしなさい。
といった風に、様々な制約をかけられています。
幼いころはそれを受け入れていたと思います。
しかし、成長する中で自分自身の考えができてくると、
「俺(私)はこう考えているのに、全然理解してもらえない!」
といったように、感じるようになります。
大人でも仕事の中でそのように感じますが、
違う場面でその気持ちを消化しながら、
ある程度飲み込んで、
調整しながらやっていけます。
しかし、子どもの場合は生活ほぼすべてが、
大人からの制約がかかった状態になっています。
その結果、過程の中だけでも制約から脱却しようと、
激しくもがいてしまうのです。
特に男の子の場合は、
その結果が乱暴な口調だったり、
乱暴な行動になったりしてしまいます。
女の子の場合は、
自分のテリトリーに引きこもろうと、
部屋に閉じこもったり、
無視したりするようになります。
これは自分の考えができて、
それが親の考えと違い、
そこの調整ができないまま
動いてしまっているのです。
調整ができず子ども自身もイライラしてしまい、
その結果暴力的な行動になることもあります。
しかし、これは子どもがアイデンティティを確立するために、
必要な時期だと考えられています。
私自身も、教師として、親として子どもの反抗期に接して、
この時期を経て子どもは大きく成長すると感じています。
反抗期は何歳に起きるというものではありませんし、
子どもによっては反抗期が起きないこともあります。
ある日急に態度が反抗的になり、
家庭でのケンカが多くなる場合もあるでしょう。
学校で友達と何かあったのではないかと心配になり、
電話をしてきた保護者の方もいらっしゃいます。
反抗期は子どもの成長過程で当然起きるもの、
まずはその認識をしっかりとして、受け止めてください。
反抗期の子どもへのNG対応

子どもが反抗期に突入したことによって、
親が右往左往してしまい、感情的になったりして、
その時期の子どもの対応として、
良くない対応をする場合があります。
先ほど書いたように、反抗期というものは、
多くの子どもが迎える成長の段階なので、
反抗期自体は何も問題はありません。
しかし、反抗期の時の対応があまりにひどいと、
その後の親子関係の溝へとつながっていきます。
反抗期は一時的なものですが、
それが原因で長い親子関係の歪みになることは、
意外と少なくありません。
ぜひ対応を間違えないようにしましょう。
NG対応は以下の2つです。
1 頭ごなしに怒る。話を聞かない。
2 無視をして放任する。
では順番に見ていきましょう。

子どもの言うことに足して腹を立てて、
話を聞くことも無く頭ごなしに怒る。
これが一番多いNG対応になります。
大人である親もひとりの人間です。
子どもの反抗的な態度に腹も立ちますし、
感情的に怒ることもあるでしょう。
しかし、こういった対応を毎回のようにするのは、
子どもの心を傷つける結果になりますし、
子どもは「言うことをきかない人には怒鳴ればいい」
という間違った学習をしてしまいます。
大人になった時に、思い通りにならない時に、
怒鳴り散らすような人にしたくはないと思います。
先にも書きましたが、子ども自身も、
自分の感情をコントロールできずに、
イライラしている状態でもあります。
イライラに対してイライラを毎回ぶつけていては、
子どもが感情をコントロールする機会を、
奪ってしまうことになります。
腹の立つ態度をとられてもぐっと我慢して、
話を聞いてあげることを繰り返すことで、
少しずつですが、
子どもは冷静に話ができるようになります。
納得いかないことだったとしても、
時には子どもの言うようにしてもいいでしょう。
もちろん毎回言いなりになるのは、
子どもがこれでいいんだと、
勘違いをするのでやめましょう。
イライラすることもあるとは思いますが、
大人として大きな心で受け止めてあげましょう。

あまりに腹の立つことばかりするので、
もうこの子の行動は無視しよう。
何もしゃべろうとせずに無視してくるから、
私も何も話しかけないでおこう。
そんな発想に至るかもしれません。
しかしそれはいけません。
ある程度目をつぶってあげるということは、
子どもにとっては必要なことです。
しかし、無視されている、見捨てられた。
そんな風に子どもが感じるのはダメです。
この状態が続いてしまうと、
親も子どもの状態がどういう状態か分かりません。
ひょっとしたら反抗期が終わっているのに、
会話がない状態が続いてしまう。
そんなことになってしまうかもしれません。
今までしっかりと愛情を注いできたのなら、
子どもは心の中ではいつも親を意識しています。
子どもの態度がどうであろうと、
常に子どもに寄り添う気持ちは必要です。
無視をせず、何気ないタイミングで声をかけて、
あなたのことをちゃんと見ているのよ。
そんなサインを送り続けてあげてください。
最後に

偉そうにいろいろと書きましたが、
私自身も長男の反抗期にはかなり手を焼きました。
「てめえのことなんか親と思ってねえよ!」
そんな言葉を聞いたときには、
思わず泣いてしまったこともあります(笑)
そんな息子ですが、中学3年生の終わりごろから、
急に落ち着ていて話ができるようになりました。
ぐっと心が成長した息子と、
今は大人同士の会話をできるようになっています。
いままで注いだ愛情は絶対に裏切りません。
反抗期でつらい思いをされているおうちの方、
後で笑い話になる日が必ず来ます。
これまで通り子どもに愛情を注いであげてください。

こちらもよく読まれているページです
- 夫の支えがないワンオペ育児
- ワンオペ育児とは、配偶者の単身赴任など、何らかの理由で、1人で仕事、家事、育児をこなさなければならないそういった状態を指します。1人ですべてをこなしていると、支えてくれる人もおらず、頼れる人もいない、子どもはかわいいけれど自分の体はボロボロ。そんな状態になってしまいます。今回はワンオペ育児になりそうで心配な人または現在進行形でワンオペ育児だ!そんな人に向けて書いていきます。
- 小学生の習い事は何がいい?
- 一言で習い事と言っても、運動系や芸術系、勉強系など、様々です。選択の幅が広がったぶん、一体何の習い事をやらせればよいか、迷ってしまう保護者の方も多いようです。今回は小学生の習い事について、おすすめや考え方について書いていきます。
- 反抗期の子どもに話をする方法!
- 反抗期の子どもと話をすると、イライラした態度をとられてしまい、ついついこちら側も感情的になってしまいます。私もクラスの中で合わない子どもと話すと、あちらの態度に感情的になってしまいどうしても口調が強くなってしまいます。クラスの子どもであれば、他人の子でもありますし、私も仕事として冷静にやっていくこともできます。しかし、自分の子どものこととなると、そうはいかないでしょう。私が反抗的な子どもと関係をきずいて、私の話を聞いてもらえるようにする時には、いつも気を付けていることがいくつかあります。自分の子どもが反抗期の時にも、このポイントを押さえていると、自然とうまくいくようになりました。
- 小学生のスポーツやピアノの習い事
- 子どもが習い事に没頭して、自主的に練習をしたり、指導者の方がしっかりと面倒を見てくれたりと、良い状況になることもあります。しかし、多くの場合は、思ったより子どもが変化することなく、しばらくすると子どもも習い事に後ろ向きになり、辞めてしまう流れになるでしょう。習い事を一生懸命やる子どもと、 そうではない子ども。一番の違いは何でしょうか?それは親の考え方と行動です。今回は習い事を始める時に、親も覚悟をもって始める必要性について、書いていきたいと思います。
- 子どもの将来が不安?
- 子どもの将来を憂いている親はとても多いです..。しかし、将来を心配している親に、「お子さんに将来どうなっていてほしいですか?」という質問を私がすると、意外と何もない場合がほとんどです。でも、どんな親も「幸せな人生を歩んでほしい」という考えは共通しているはずです。今回は、今目の前の子どもと向き合いながら、将来について考えることについて書いていきます。
- 反抗期がない子ども
- 反抗期というのは子どもの自立期でもあります。この時期が無いというのは、自立する機会を失っている可能性があります。反抗期がない=それは良いことである。この認識は間違っていると思いましょう。今回は反抗期がない子どものタイプ別と、心配される将来について書いていきます。
- 叱るとふてくされる?
- 叱った時にふてくされた態度をとるのは、小学生の特に高学年になるとよくある反応です。思春期に入った子どもは、自立に向けて自分という存在を守ろうとします。小さいころのように叱ったとしても、素直に受け入れることは少ないでしょう。叱られた時に素直にじっと聞いていて、お母さんにごめんなさいと言う。そんな小学生はほとんどいないと考えましょう。では子どもがふてくされた態度をとった時、あなたはどういう対応をしますか?
- いじめられない子どもにする方法!
- いじめる子どもといじめられる子ども。この構図はどこの学校でも、必ず見られるものです。いじめは許されないことですし、この世の中から無くなってほしい。私も教員として心から願っています。しかしながら、いじめが無くなるというのは、戦争を無くすのと同じくらい難しいことです。せめて自分の子どもだけでも、その被害を受けないようにしていきたい。そう思う保護者の方も多いでしょう。 今回はいじめられない子どもにするために、 大切なポイントを紹介します。
- 子どもがお手伝いをしない?
- ちょっとくらいお手伝いしてくれてもいいのに、うちの子家で全然何もしない。私の感覚で話をさせてもらえば、勉強が多少できなくてもお手伝いなどを、しっかりとやれる子どもの方が、将来、力を発揮すると思います。今回はお手伝いがなぜ大切なのかという話を書いていきます。
- お手伝いができる子にする!
- 子どもが家でゴロゴロ、お願いしても、やってくれない。最終的には子どもを説教する。そうなっているご家庭も多いのではないでしょうか。そんな子どもがお手伝いのできる子に、変わってくれたら嬉しいですよね。今回は、お手伝いができる子にする方法について書いていきます。