小学生の算数の勉強方法②小数や分数を理解させよう!
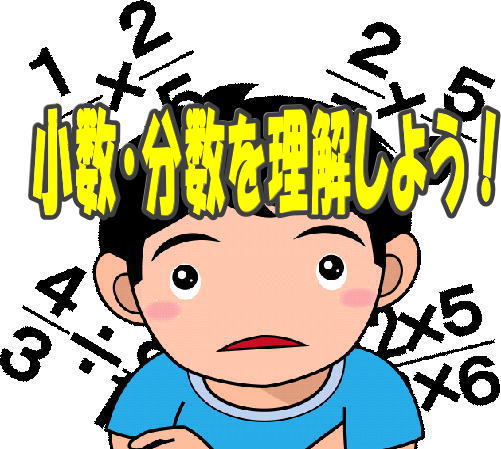
小学生が壁にぶつかるひとつ。
算数の小数と分数。
小学校3年生の内容です。
この小数と分数ができないと、
小学校だけでなく中学、高校と、
数学だけでなく理科までできない。
そんな状態になってしまいます。
この小数と分数ができるというのは、
計算ができるということだけではなく、
小数・分数の量的な感覚があるということです。
ここでは計算ができるだけはなく、
量的な感覚を身につける大切さと、
身につけるために必要な力のつけ方について、
書いていこうと思います。
小数と分数の計算ができるようにする!
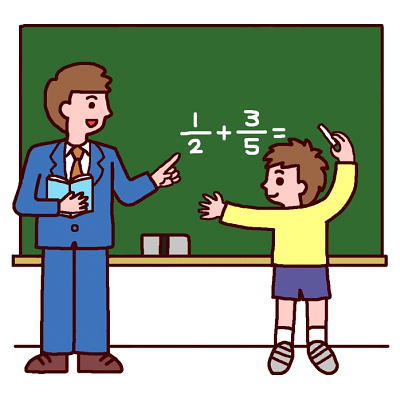
小数と分数の計算ができるようにするには、
まず第一に練習量が必要です。
つまり、たくさん解いて感覚を身につけるのです。
たくさんやればできるようになる
と言ってしまうと元も子もないようですが、
これをやっていない子がほとんどです。
たとえば0.5×0.5という式。
応えは0.25なのですが、
5×5をやった後に、小数点以下の数字の数だけ、
25の後ろから動かしていくのです。
今回は0.5と0.5で小数点以下が2個
25→2.5→0.25といった感じです。
小数の掛け算はこのルールさえ守っていれば、
誰でもできるはずなのに、
多くの先生はこのルールを徹底させません。
というか、このルールが染みつくまで、
反復練習をしていないのです。
簡単な問題でこの計算を繰り返せば、
必ず少数の掛け算ができるようになるのです。
あとの計算は応用であり、
基礎ができればできてしまいます。
分数も一緒です。
1/2+1/3という問題。
分母の2と3の最小公倍数6を見つけて、
3/6+2/6=5/6
最小公倍数を見つけるには、
何のこれ式を繰り返すのがおススメです。
ここまでの話で何が必要かというと、
このルールを意識しなくてもできるまで、
繰り返しやり切れるかどうかなのです。
サッカーをやる時に、ドリブルがぎこちない状態で、
試合で活躍できるわけはありません。
基礎的な計算についてはとにかく練習です。
分数や小数の習いたての時に、
苦手な状態で放置しておくことで、
後々の計算がとにかく大変になります。
私が以前5年生の担任をしていた時に、
クラスで分数の足し算ができない子が、
クラス全体の半分以上だった時がありました。
その学年は3年生、4年生と学級崩壊していて、
基礎的な計算能力が著しく低い学年でした。
何とか時間をやりくりしながら、
計算を一からやり直して、何とか全員、
ある程度までは計算ができるようになりました。
どんなにすごい先生だったとしても、
子どもに計算の基礎を定着させるには、
時間がかかってしまいます。
計算の基礎部分に関しては一日に少しでいいので、
毎日トレーニングさせる必要があるでしょう。
小数と分数の量的な感覚って何?

計算ができる子でも、意外と無いのが、
小数と分数の量的な感覚です。
1/3と0.5のどちらが大きいか。
5/2が3より大きいか小さいか。
もちろん計算すればできるのですが、
計算の前に、感覚としてこれが欲しいのです。
例えば3×0.25を7.5と答える子。
計算ミスと言えばそうなのですが、
元より大きい数字になった時に、
何の疑問も持たないことが問題です。
この数量的な感覚というのは、
テストで100点をとるような子でも、
あまり無い子が多いのです。
この感覚をしっかり身につけるには、
日常的な生活の中で分数や小数について、
意識させることが必要になってきます。
10両の電車と6両の電車があった時に、
これは何倍か、何分の一か。
具体物で行うことでしか身に付きません。
私は給食の時間に牛乳を1/3まで飲む。
ごはんを0.4倍に減らす。
そんな風に伝えることで、
少しでもこの感覚を身につけるようにさせています。
先ほどの計算と同じように、
繰り返しの練習が必要ですし、
感覚が身についたかどうかというのは、
確認する方法が難しいです。
しかし、知識を活かして行動する。
この行動のリンクが理解をより深いものにします。
中学校の理科の中で、
濃度や湿度を求める問題があります。
この感覚が無いまま分数や小数を使っていると、
イメージが全く湧かないでしょう。
計算の基礎を身につけると同時に、
具体的なもので感覚を身につける。
これで、その子は一生、小数と分数で、
困ることは無いと思います。
最後に

小数や分数の計算がスムーズにできる。
私はこれを小学校の段階で、
最低限身につけなればならないことだと考えています。
文章題が苦手、単位があやふやである。
これは、その部分を練習すれば、
中学校からでも何とかなるものです。
しかし、分数や小数の計算までは、
中学校でやり直してくれることはまずありません。
その部分はできる前提で授業が進んでいき、
計算が苦手なことを隠しながら、
子どもはどんどん授業についていけなくなります。
学校の授業だけで子どもができるようになるほど、
甘いものでは無いと認識して、
心を決めて子どもに練習をさせましょう。

こちらもよく読まれているページです
- 小学生の国語の勉強方法①
- 国語の勉強ができない子は、算数の文章題も苦手です。社会や理科の問題の読み取りが苦手です。国語という教科は、全ての教科に通じるといっても過言ではありません。そんな国語の能力を上げるためには、音読がまず大切です。
- 小学生の国語の勉強方法②
- 漢字の練習は、何度も書いたり、読み方や送り仮名を知ったり、正直地味な勉強で、特に男の子は、嫌いになりやすい分野です。しかし漢字の読み書きができないことには、国語の勉強は進まないでしょう。できれば楽しく勉強して、見についてくれればうれしいですよね。
- 小学生の国語の勉強方法③
- 国語の勉強をするのは、最終的には日本語の文章を、困らない程度に書けることが必要です。そのための素地はどこで学ぶのか。それは小学校の間でしょう。きちんとした文章が書ける人は、文章を読んだり理解したりすることが、できるようになります。
- 小学生の国語の勉強方法④
- 国語の勉強をする上で、いわゆる活字慣れをしているというのは、大きな強みです。また、分からない単語というのも、ボキャブラリーが増えれば減りますので、それだけ読解力が上がるでしょう。今回は子どもの読解力を上げるために、本やマンガをたくさん読むことの、大切さについて書いていきます。
- 小学生の算数の勉強方法①まずは足し算引き算掛け算割り算!
- 中学校で教員をする主人が、「読み書き計算だけは小学校でやってほしい」ということをよく言っています。小学校の高学年で、算数が苦手な生徒というのは、基礎的な計算が、出来ないか遅いかのどちらかの場合がほとんどです。今回は算数が苦手な子どものために、足し引き掛け割り算をさせるための、 コツと大切さについて書いていきます。
- 小学生の算数の勉強方法③
- 小学生で文章題が苦手な子はとても多いです。基礎的な計算が結構できる子でも、この文章題で間違えて100点を逃す。そんな子が多いです。うちの子は本を読まないから苦手なんです。そんな風に言う保護者の方がいますが、私はそれは違うと思います。算数の文章題というのは文章→計算式という変換が必要なため、ただ単に本をよく読んでいるかどうか、というのはあまり関係がありません。それよりは、ミスなくきっちりと、文章を読み取る力が必要なのです。
- 小学生の体育の練習方法①
- 小学校の教員を続けていく中で、ゆるやかに、しかし確実に、子どもの体力はさがっていっているのを、 日々感じています。また、体力の格差も激しく、運動系の習い事をしている子どもは、体力を上げていき、そうでない子は、体力が無い状態になっていきます。体育の運動をしていても、すぐにばててしまう子どもが、とても多いように感じています。まずは基礎体力をしっかりとつけないと、体育だけでなく、学校生活全体が、活力のないものになってしまいます。
- 小学生の社会の勉強方法①
- 小学校5・6年生の社会からは中学でも使う、地理や歴史が入ってきます。中学校でもう一度やるとは言え、小学校のうちに覚えておけば楽になります。社会は暗記科目として考えられて、苦手だった保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし、一時的に暗記する力というのは、そもそも人によってそこまで差がないのです。大切なのは知識同士をつなげる力、何度も繰り返して記憶を定着させる力、そういった力を鍛えることなのです。